成年後見制度は、判断能力が不十分な人の財産や権利を守るための制度です。
成年後見制度は、すでに判断能力が不十分な場合の「法定後見」と今後に備えて契約を結ぶ「任意後見」があります。
法定後見について
高齢や障がいにより判断能力が不十分な方のために、保護・支援する人を選んで、生活や財産に関することを行い、その方の権利を守るための制度です。
成年後見人の役割
成年後見人の仕事は本人の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援します。
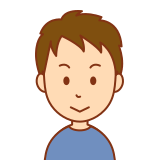
身上監護と財産管理ですね
成年後見人はどんな人がなるの?
家庭裁判所に申し立てるときに、後見人にしたい人の候補者を提出できます。
成年後見人は特に資格は必要ないので、親・子供・兄弟などの親族を候補者にすることも可能です。
また専門職後見人として裁判所の後見人候補者名簿などに登録のある司法書士、弁護士、社会福祉士などが指名されます。
養成講座などで知識を身につけた一般市民に市民後見にとして活動してもらうこともあります。
*ただし誰にするかを実際に決めるのは家庭裁判所です。
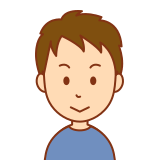
家族などを後見人にした場合に、被後見人である本人に、ある程度の財産があると、専門職後見人を指名する傾向がありますね。
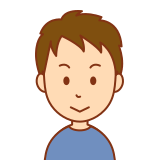
最近は親族と専門家、社会福祉士と弁護士などの複数人後見や法人が後見人になるケースも増えてきてます。
申し立てのできる人
申し立てができる人は本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長です。
必要な書類
申立書、戸籍謄本、住民票、医師の診断書、財産関係のわかる資料(通帳など)
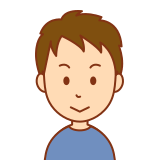
家庭裁判所に申し立てをします。書類をそろえるのは大変です。司法書士や弁護士に手続きをしてもらうといいでしょう。
3つの類型 後見 保佐 補助
後見、保佐、補助の判定は医師の診断によります。決定するのは家庭裁判所です。
後見とは?
対象者
判断能力が全くない人です。常時、判断能力が欠けた状態の人です。(日常的な買い物にも支援が必要な人)
同意権の範囲
ないです。
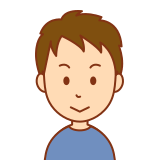
被後見人には判断能力がないので、後見人が同意しても、そもそもその通りの行為ができないからです。
*同意権とは~例えば誰かの借金を依頼された場合、保佐人、補助人などの同意がなければ、なることができません。
取消権の範囲
日用品の買い物などの日常生活に関する行為を除くすべての法律行為です。
*取消権とは~本人が行った、本人にとって不利益な契約を取り消すことができます。
代理権の範囲
財産に関するすべての法律行為です。
*代理権とは~特定の法律行為(契約など)を本人に代わって行うことのできる権限を言います。
保佐とは?
対象者
判断能力が著しく不十分な人です。(不動産の売買など、重要な財産の契約は難しい人)
同意権・取消権の範囲
借金、相続関連など民法で定められた財産に関する重要な行為などです。
*同意権とは~例えば誰かの借金を依頼された場合、保佐人、補助人などの同意がなければ、なることができません。
*取消権とは~本人が行った、本人にとって不利益な契約を取り消すことができます。
代理権の範囲
申し立ての範囲で裁判所が定める行為で本人の同意が必要です。
*代理権とは~特定の法律行為(契約など)を本人に代わって行うことのできる権限を言います。
補助とは?
対象者
判断能力が不十分な人です。(ほとんどのことは自分でできるが、何かの時は補助してほしい人)
同意権・取消権の範囲
借金、相続関連など民法で定められた財産に関する重要な行為の中で、申し立ての範囲内の中で裁判所が定める行為で、本人の同意が必要です。
*同意権とは~例えば誰かの借金を依頼された場合、保佐人、補助人などの同意がなければ、なることができません。
*取消権とは~本人が行った、本人にとって不利益な契約を取り消すことができます。
代理権の範囲
申し立ての範囲で裁判所が定める行為で本人の同意が必要です。
*代理権とは~特定の法律行為(契約など)を本人に代わって行うことのできる権限を言います。
こんな時に成年後見制度を利用します
使うはずのない高額な商品を頼まれるとつい買ってしまう。
認知症の親の不動産を売却して介護施設の入所費に当てたい。
親が死んだあとの、知的障害の子どもが将来が心配。などなど。
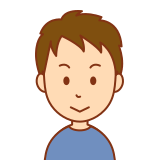
他にこんな理由もあります。親の財産管理をしてきたけど、他の兄弟から疑われている。介護施設にいる親の年金を勝手に兄が持ち出して困っている。などなど。

任意後見制度とは?
元気なうちに、将来に備える制度です。
どんな内容?
元気なうちに、自分で選んだ任意後見人との間で、判断能力が低下した時にお願いしたいこと、例えば財産の管理や生活の支援などを決めておきます。
任意後見契約
公証役場において、任意後見人なる人との間で、任意後見契約を結びます。
任意後見開始
任意後見人が任意後見契約に基づいて、本人のために支援を開始します。
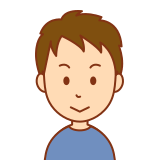
家庭裁判所に任意後見監督人を選出してもらい、任意後見人の仕事をチェックしてもらいます。任意後見人と任意後見監督人に報酬が発生します。
この本は、弁護士が書いた本ですが、親族がいろいろと質問するという設定になっています。Q&A方式になっていて、また図解も多く、とてもわかりやすく書かれています。豆知識として注意すべきポイントについてもふれています。役に立つ本です。
この本は愛読書です。お子さんが生まれたときから、大人になってからのことまで、そして親が死んだ後のことまで、書かれています。法律や制度についても、わかりやすく書かれています。将来に不安を感じている方は、特にオススメします。福祉や教育の関係者の方にも、この本はオススメです。
この本は、障害者総合支援法について、こらから、学ぼうとしている人にとてもわかりやすく記述されています。また、福祉や教育の関係者の方にも、ピンポイントで知りたい情報を得られるので、ハンドブックとして、とても便利です。この本もオススメです。





コメント